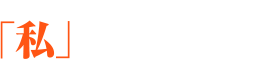怪物のデザイナーと少年 山川健一
山川健一、7年ぶりの新作小説──
次代のプロ作家を育てるオンラインサロン『「私」物語化計画』会員用Facebookグループ内の講義を、一部公開いたします。
ご興味をお持ちの方は、ぜひオンラインサロンへご参加ください。

→ 毎週配信、山川健一の講義一覧
→ 参加者募集中→ 参加申し込みフォーム
「私」物語化計画 2022年6月3日
特別公開:怪物のデザイナーと少年 山川健一
2022年6月3日金曜公開分の講義に代えて、7年ぶりとなる山川健一の新作小説を一部掲載いたします。なお来週はこの小説をベースに「私」ノート実践編となる予定です
怪物のデザイナーと少年
山川健一
古いマンションの三階の広いテラスで俺は夜空を見上げる。漆黒の闇を切り裂いて、オレンジの炎を吐き轟音を立てながらミサイルが飛んでくる。
そいつは空の彼方にあらわれたかと思うと、真っ直ぐにこちらにおちてくる。
くそっ、迎撃しないと。
だがそんな暇はありはしないのだ。
ミサイルにやられ、建物は砕け散る。コンクリートの破片が飛び散り、俺はしゃがみ込んだ。
テラスに敷き詰めた人工芝を叩き、それからゆっくり息を吐いた。
ミサイルは飛んではこない。
ここは東京なんだと自分に言い聞かせる。ウクライナではない。ほっとして見上げると、渋谷の街に聳えるビルの上で明滅する赤いランプが見えた。昼間はその上を空港を目指す旅客機が飛んでいく。
夜の闇の彼方では、実際にロシア軍のミサイルが飛んでいるだろう。そいつはマンションや病院や学校に落ちて、建物は瓦礫になり、多くの人間が手足や頭を吹き飛ばされて死んでいく。
ボールをつきながらマンションの鉄の外階段を誰かが登ってくる足音が聴こえる。テラスの鉄柵の向こうの階段に子供の姿が現れた。
「なにやってるの?」
俺は夜空を指差し、
「ミサイルがな──」と言いかける。
小学五年生のバスケットボール・ボーイ、俺の友達の翔太がこの部屋に続く短いエントランスを駆け上がり、柵を乗り越えてテラスにやって来る。
ライトブルーのシャツと白いパンツのバスケのユニフォームを着た翔太は、しゃがみ込んだ俺の周りをボールをドリブルしながら回る。小学生なのにテクは抜群で、フェイントをかけられると絶対にカットできない。
「飛んでくんの、ミサイル? 日本も戦争するの?」
「いや、しないよ。でも見えた気がしたんだよ」
ドリブルしながら夜の闇に包まれたテラスを軽快に動く。
やがて翔太はドリブルをやめ、ボールを置いてその上に腰かけた。眼が少し怯えている。
「はぁ? それってあなたの感想ですよね?」
ヒロユキの真似だ。
「こんな時間に小学生がフラフラしてていいのかよ。ママは?」
「ヤキン」
「──夜勤か。たいへんだな」
翔太のママは看護師でシングルマザーだ。彼女が勤務する病院は新型コロナの患者を受け入れている。二人は四階の部屋に住んでいる。
俺が翔太と知り合ったのはマンションの下の公園の、球技用のケージの中だった。その時翔太達はバスケではなくサッカーをやっていて、こぼれ球を蹴り返してやったらいっしょにやろうと誘われた。
一時間ほどサッカーをやったらヘトヘトになり、足がもつれそうになった。俺は思わず熱くなりシュートを決めようとして、右足がボールに乗り転倒して右肩から落ちた。激痛を堪えていると翔太がやって来て言った。
「カッコわるぅ、早く立てってば! みんな見てるじゃん」
肩の痛みが治るのに一年以上かかった。クソガキめ、猿め。大人は子供みたいに身軽には動けないんだよ。
俺は立ち上がる。
「腹減ってないか。カップ麺ならあるぞ」
「食べたい」
俺はテラスを歩いていき、リビングに続くガラスのドアを開けた。翔太がテラスではなく部屋に入るのは初めてのことだった。
「ウサギが放し飼いだからな」と俺は言う。
翔太が部屋に入ると、野ウサギのメイが白い尻尾の裏を見せながら廊下の方へ駆けていった。
小さな男の子の背中がフリーズしている。ウサギのせいかと思ったら、そうではない。彼の視線は壁に貼ったポスターに注がれている。
「ザ・シャークだ──」と翔太。
「そうそう、俺が描いたんだぞ」
ゆっくりと、ボールを抱えたまま翔太がこちらを振り返った。翔太の向こうには、空中を浮遊する獰猛なサメのポスターがある。
「描いた? オジサンが?」
「話したことなかったっけ。俺の仕事はクリーチャー・デザイナーなんだよ。ゲームに出てくる怪物の原画を描くのさ」
俺は翔太をアトリエ用の部屋に連れて行き、原画のラフスケッチを見せてやった。
「スゲェ!」
「俺の原画をゲーム会社の社員のグラフィッカーが書き起こして、そいつを3Dモデラーが立体にするんだよ」
翔太がキラキラした眼で俺を見上げている。ハハ、少しは尊敬したか、これ以上馬鹿にするのはやめろ。
カップ麺を食べながら、翔太はザ・シャークを何度も見上げた。他にも得体の知れないクリーチャーの絵が何枚か貼ってある。
「こんな気持ち悪いモンスターをさ、よく思いつけるよね」
「だよなぁ。俺もさ、自分で気味が悪いことがあるよ」
それから俺は自分の胸を指差した。
「みんな、ここから生まれた。怪物がさ、胸の中に棲んでるんだよ。ザ・シャークはしばらくこの床を泳いでた」
深夜のリビングをシャークがゆっくり泳いでいるのを見た時、最初、俺はぎょっとした。強迫神経症の一種なのかもしれないと考えた。しかし医者には行かなかった。職業病だと割り切ることにした。
翔太が何と言うか、俺は顔を覗き込んだ。
「ちょっと意味がわからない」
彼は立ち上がると棚に飾ってあったFGOの愛らしい少女戦士キャラ、マシュ・キリエライトのフィギュアを取ってきてテーブルに置く。
「僕はマシュのほうがいいな」
翔太はクラスの女子の人気者なのだという話を思い出した。彼の友達の女子がそう言っていたのだ。バスケやクロスカントリーが得意で優しい性格だから、女子にも男子にも好かれるのだろう。
「おまえ、クラスでモテモテなんだってな。カリンがそう言ってたよ」
「うるさいよ、カス、ゴミ、ジジイ!」
俺はカップ麺の汁をすする。
公園で翔太に学校のテストを見せてもらったことがあった。保健体育のテストの「思春期になるとあなたはどうなりますか」という問いに彼は「生理になる」と答えてバツをつけられていた。俺は笑い、馬鹿じゃねーの、おまえには精通ってのが来るんだよと教えてやったことがある。
「ロシア軍はここまでは攻めてこないの?」
翔太が思い出したようにそう聞いた。
「今のところはな」
「もし来たら?」
俺は少し考え、答える。
「戦うしかないかな」
「ジャベリンで? アサルトライフルで?」
小学生達はフォートナイトというゲームをやっているので、武器の種類には精通している。
「核ミサイルを撃ち込まれたら終わりだけどな」
野ウサギのメイがやって来て、俺の脚に前足をかけ、ニンジンをねだった。
夜、十時過ぎだ。
緩やかに降る歩道を、俺はジーンズのポケットに手を突っ込んだまま歩いていた──続きはオンラインサロンでご覧ください)