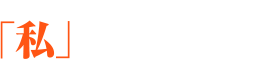特別全文公開:キャラクター・メイキングの段階 1 『私を見て、ぎゅっと愛して』(七井翔子) 山川健一
物語という表現形式の、光り輝くパラドックスである──
—
次代のプロ作家を育てるオンラインサロン『「私」物語化計画』会員用Facebookグループ内の講義を、特別に全文公開いたします。
ご興味をお持ちの方は、ぜひオンラインサロンへご参加ください。

→ 毎週配信、山川健一の講義一覧
→ 参加者募集中→ 参加申し込みフォーム
「私」物語化計画 2021年5月28日
特別全文公開:キャラクター・メイキングの段階 1 『私を見て、ぎゅっと愛して』(七井翔子) 山川健一
今週から何回かにわたり、キャラクター・メイキングについて講義します。これまでにレクチャーした物語と小説の構造を頭の引き出しから取り出しながら読んで下さい。
作品のキャラクターを創造するのは、ストーリーを作ることと密接に繋がり、さらに作家の個性にも深く関係している。非常に重要である。
キャラクターはストーリーの進行と共に成長していくことはあっても、途中でブレてはいけない。登場人物の「変化」は、受け手が納得出来るものでなければならないのだ。
さらに、とりわけ主人公は、強烈なインパクトを読者に与える存在でなければならない。それは、例えば静謐な恋愛小説でもそうなのだ。物静かな女性が、眩い光を内側から放っていなければならない。児童文学でも同じである。一人の子供の魂が強い輝きを放っているからこそ、読者は感動する。
小説でも映画でもゲームでも、僕らはストーリーや哲学の全体を登場人物達の存在として思い出す。キャラクター・メイキングはそれだけ重要なのである。
むしろキャラクターが先に存在し、ストーリーは彼が歩いた後ごく自然に出来上がっていく──というのが理想だろう。
もう一つ言えば、継続して書き続けている作家が、どんなに魅力的なキャラクターを創造したとしても、それまでの作品となんの脈絡もないキャラクターであったなら読者は納得しないだろう。作品のキャラクターは作家自身の個性にも深く関係しているからだ。
例えば僕がある日藤沢周平を思わせる時代小説を書き上げることが出来たとしても(絶対に無理だが)、多くの人達は「何、これ?」と思うだけだろう。
それは、山川健一という泥の中から芽生えて咲いた花ではないからだ。
どうすればそんなキャラクター・メイキングが可能なのか。お教えしよう。「ジェノバの夜」を振り返ればいいのだ。
キャラクター・メイキングの具体的な方法には段階がある。
- 神のデザイン
- 英雄のデザイン
- ゲマインシャフトによるデザイン
- ゲゼルシャフトによるデザイン
- 意識の対象化によるデザイン
- 「ジェノバの夜」の対象化
またヤマケンが小難しいことを言い始めた──と思ったあなた、まあ、まあ、まあ、最終的にはシンプルでわかりやすい結論になるのでちょっと我慢して読んでください。
これは神話に始まり現代小説に至る文学史のキャラクター・デザインの方法を振り返ったものだ。
まず神話があり、そいつが英雄譚に進化し、やがて普通の人間が主人公の物語が誕生する。
しかしまだそれは、個性的な個人の誕生には至らず、まずゲマインシャフト(共同体)の中の役割がキャラクター創造のキーになった。
厳格な父親とか優しい母とか家族での役割や、郷里を同じくする親友──というようなパターンだ。
ゲマインシャフトは地縁・血縁・精神的な繋がりにより自然発生的に形成した集団。家族や村落などだ。ゲゼルシャフトは目的や利害を達成するため作為的に形成した集団で、近代国家における会社での役職や職業そのものをキャラクターにするパターンだ。上役と部下とか、ライバル会社の男──という具合だ。バルザックが典型的だろうが、チャンドラーのハードボイルドに登場する私立探偵などもそのバリエーションである。
やがて「自意識」を扱う作品がドストエフスキーなどによって書かれるようになり、神々でも英雄でもなく、父親でも息子でもなく、会社の上司や部下でもなく「自己を意識する私」が主人公になっていく。
そして今、多くの作家達は自らの「ジェノバの夜」と向かい合うことで主人公を造形しているのだと僕は思うのだ。
『「私」物語化計画』では基礎コースでも実践コースでも、最初の課題は「自分にとってのジェノバの夜とは何だったのか」というレポートを書いてもらうことなので、全員がこの課題に取り組んだはずだ。
まだの人は今からでもいいので送ってください。
ポール・ヴァレリーは若い頃、一回りも年上の人妻に恋をしたのだが叶わず、自殺を決意し母親と一緒にイタリアのジェノバへ旅をする。ジェノバを記録的な嵐が襲い、ヴァレリーは窓ガラスに叩き付ける雨と強い風の中で、自殺を思いとどまり自分の中に新しい人格を誕生させるのだ。それがテスト氏だ。
知的クーデターの経験だ。
「ジェノバの夜」と向かい合うことは、自分自身が「私」を生み出す作業である。
あなたにも象徴的なそういう夜があったはずなのだ、それを思い出してください──というのがレポートのテーマだった。
ジェノバの夜は文字通り一夜のこともあれば、数年にわたることもある。さらに、僕らの長い人生には複数回のジェノバの夜が訪れることもある。
その体験の意味を深く理解出来た時にこそ、僕らは新しい一歩を踏み出せるのであり、そのためにこそ小説を書くのではないだろうか。
そして列挙したキャラクター・メイキングの段階は、今では並列的に僕らの目の前にある。つまり、もはや新しいも古いもないのだという意味だ。
僕が今いちばん好きなゲームは『Fate/Grand Order』だが、Fateのキャラクター・メイキングの方法は神のデザインと英雄のデザインに依拠している。
バルザックの作品の登場人物たちはゲゼルシャフト・デザインによって描かれるが──貴族かそうでないかとか、医学生だとか盗賊だとか──これも古いとは言えない。
藤沢周平の時代小説はどれも爆発的に売れているが、海坂藩という架空の藩を舞台としたものが多い。風土の描写は、彼の出身地の前身である庄内藩とその城下町、鶴岡がモチーフになっている。
下級武士、上級武士、殿様、農民、忍者──などの社会的な属性によってキャラクターの多くの部分は決定されるわけで、これはほぼバルザックの手法と同じである。
キャラクター・メイキングの段階が今や並列的にあるとはそういう意味だ。あなたはどの手法を使うことも許されている。
ただし、これには条件がある。
それはまず最初に「ジェノバの夜」の対象化を終えている必要があるということだ。『Fate/Grand Order』や藤沢周平の時代小説から皆さんが書いている現代小説まで、事情はまったく同じである。
【『私を見て、ぎゅっと愛して』(七井翔子/河出文庫)におけるジェノバの夜】
ジェノバの夜の対象化にもっとも有効な方法は日記を書いて見ることだ。ノートと言ってもいい。
その日記、ノート、手記が小説以上の力を持つ文学作品に結実することがある。
学生運動の活動家で自殺した奥浩平の『青春の墓標』や高野悦子『二十歳の原点』は多くの人々に読まれ、僕らに強烈なインパクトを与えた。
ジム・キャロルの『マンハッタン少年日記』(晶文社)はレオナルド・ディカプリオの『バスケットボールダイヤリーズ』の原作だが、僕はこの日記にジャック・ケルアックの『路上』以上の影響を受けた。
ポール・ヴァレリーの『テスト氏』に始まる日記文学(ノート文学と言うべきか)には、僕らがキャラクター・メイキングについて考える時に学ぶべきものが多い。
今年になって文庫本を送って頂いた。七井翔子さんの『私を見て、ぎゅっと愛して』という上下巻の作品だ。
僕は初めて接する作品だったが、2006年に単行本が刊行され、その前にはブログで連載されていたとのことだ。15年経ってようやく、文庫化されたことになる。いわば出版シーンの小さな奇跡だろう。
この作品は小説ではなく日記、いわば手記であるが、それだけにかえって鮮やかに一人の表現者のジェノバの夜が刻印されており、必読だと僕は思う。ポール・ヴァレリーの本より、七井さんの作品は僕ら現代人にずっと近く、この例を読むとジェノバの夜がどんなものかわかりやすいだろうと思う。
諒一という温厚な婚約者がいるにもかかわらず、出会い系サイトで会う複数の男達とのセックスをやめられないセックス依存症の「七井翔子」が、他にもさまざまな精神疾患を抱える日常を綴っている。
七井翔子さんの『私を見て、ぎゅっと愛して』は、リアルである。僕の周囲にも彼女のような女性は実は案外と多く、しかしこれほど鮮やかに言語化出来た人はいない。
真夜中、どうしても眠れずに書き手の翔子は睡眠薬の量を増やす。頭の芯が冴え切ってくる。彼女はベッドから起き上がり、寒さと不安で震える指でパソコンに触れるのだ。
出会い系サイトのメッセージボックスには、いくつもの欲望にまみれたメッセージが届いている。それを、読む。
……ああ、面倒くさい。こんな手続きはいいから早く寝たい。誰でもいい。早く誰かと寝たい。ほら、早くここに来て。私を抱きしめて。壊して早く、早く、早く……。心の奥から怒濤の如く、黒く赤く、熱いものが沸き立ち叫び始める。その叫びは私の指先から次々と溢れ始め、パソコンの画面に吸い込まれていく。溢れた私の叫びはきっと明日には誰かに拾われ、また私は誰かに抱かれ、悦びの声を上げるのだ。唐突に、背中の真ん中へんに虚無が襲う。いけない、いけない。それを見てはいけない。感じてはいけない。私は虚しくなんかない。悲しくなんかない。急に襲ってきた自己嫌悪の波を必死で振り払いながら、私は白い錠剤が連れてきた睡魔にようやく抱かれ、やっとやすらぐ。私の眠りは、いつもこんなふうに引き裂かれるように始まる。
彼女は国語の塾講師で、趣味で『源氏物語』を読んだりしている。生徒からの人気は高く、そのモテ具合から推察するに、おそらくは容姿端麗である。人見知りだが、長く付き合っている恋人がいて、結婚する予定だ。
もうすぐ三十四歳になる。
恵まれた生活を送っているように、周囲からは見えるだろう。だが、内面的にはそうではないのである。
リストカットしたところで、決して心の不安が消えないことはとうの昔にわかっている。もうそんな子供じみた行為は卒業したはずだ。
机の抽斗の奥に錆びたカッターを見つける。私はゆっくりと刃先を出してみる。左手の人差し指に尖った部分を当てると、血液が滲む。小さな丸を描いた私の血は、紛れもなく母から受け継いだものだ。舌先で人差し指を舐める。鉄の味がする。すぐに血は止まるが、動悸が始まるのを感じる。鈍い地響きのような鼓動を聞いていると、心の奥の片隅に沼が見えてくる。怖い。あの沼に引きずり込まれると私は這い上がれない。薬。薬を飲まなくちゃ。手を伸ばす。精神安定剤を切らしていることに気付く。すると不安が増大してパニックを起こしそうになる。沼が迫る。怖い。怖い。私はすぐに親友の穂波由香に電話する。
由香はこの作品でとても重要な登場人物であるが、これは後述する。
諒一は優しい男性で、しかしセックスには淡白である。部屋にやって来ても、そのまま帰ってしまうことが多い。自分の彼女と会ってセックスしない理由が、翔子にはわからない。
これは実は物語の秘密に関わる伏線である。
でも、求められていないことがわかると本当に不安になる。人として価値がないのではないかと焦ってしまう。
どこの誰とも知らない人と、もっともっとセックスしまくって、するすると奈落に陥落していったらどんなに気持ちがいいだろうと思う。きっとその陥落した穴の中は、罪を逃れようともがく人たちで溢れているだろう。でも、そんな退廃に身を置く自分を想像すると、ひどく満ち足りる自分がいる。恍惚とした気分になり、精神が安定する。
いっそのこと自分の手で深い昏い穴を穿ち、身を沈めてみたい。
そして汚穢にまみれて呼吸を塞がれ、いつか息絶えていくのだ。
ああ、なんという堕落。なんという快感。
この部分だけで、この作品の主人公が強烈なインパクトを読者に与える存在であることは明らかだ。眩い光を内側から放っている。
次の箇所もそうだ。
アパートに帰って出会い系サイトを開いてみる。相も変わらず多くの人が私に面接してと乞うている。私は行働反射的に返信する。書く手を止められない。このままではいけないと思いながら、一方でセックスしたいと衝動的に思う。そしてその衝動は強い。諒一くんを呼ぼうかとも考えたけれど、結局バイブレータで済ませる。
深夜、私を快感に導いてくれた冷たいバイブレータを水道で洗う。洗面所に立ちバイブを洗う私をもうひとりの私が俯瞰でじっと見ている。その後姿は、おそらく世界でいちばん惨めで、いちばん愚かで、いちばん悲しいものだ。
なんでこんなにこんがらがってしまったんだろう──と思いながら僕は読んでいく。愛される価値のない人間だという自虐が、翔子を痛めつける。そうすることで、彼女は心の平静を得ることが出来る。
そして作品としての問題は、この主人公がブレることなく変化させることが可能かどうかだ。必ずしも「成長」でなくてもいいわけだが、外的な出来事によって主人公は否応なく別の場所に歩いて行かなければならない。これは「いろいろ考えたから」とか「友達にアドバイスされたから」という展開ではダメで、具体的な事件によって今いる場所から叩き出されなければならないのだ。
ここが作品の成否を握る鍵であり、『私を見て、ぎゅっと愛して』のもっとも魅力的な箇所でもある。
やがて、『私を見て、ぎゅっと愛して』という長いジェノバの夜の記録は、秘密の核心に迫っていく。その秘密は幼少期の母親との関係にある。
僕が説明するより、引用した方がいいだろう。
私が心の病に罹患しているのは、幼児期の家庭環境に起因していると診断されてはいる。でも、私は半分信じて半分信じていない。今は思う。誰のせいでもないんだと。
母と父は一時、離婚寸前だった。父の浮気が発覚し、母は半狂乱になった。でも、事情を飲み込めない幼かった私は、母の癇性を黙って受容することでしか生きられなかった。
ある日、突然母は私の首を絞めた。その時の私は「死ぬ」という意識はなく、ひたすら苦しいとだけ感じながら昏倒した。お茶の間に飾ってあった竜胆(りんどう)の花だけが脳裏に刻まれ、私は堕ちていった。母は入院し、私は親戚の家に預けられた。私は今でもこの花を見ると発作的に駆け出したくなる。
渇くほど他者を欲していながら、その一方で渇くほどの孤独を欲している。この矛盾は、母親との関係に起因していたのである。
そういう女性は、実はとても多く、しかもそいつを克服するのは至難の業であるらしい。
「お母さん」私は母を呼ぶ。
お願い。ねえ、お母さん。こっちを見て。
お姉ちゃんばかり見ないで。私だってお姉ちゃん以上に賢いところもあるし、言うことも聞いてるよ、勉強も頑張ってるよ。
ね、お母さん。私もここにいるのよ、ねえ、私もお母さんのことが大好きなの、ねえ、こっちを見て、私のそばにいて。手を繋いで。お願い。
しかし、ここまでは感動的ではあっても言ってしまえばよくある話で、この作品が凄いのはこの後の物語の黄金的構造の展開なのである。
ネタバレを含むので知りたくないという方は読まないでください。
諒一の秘密。
そして由香の秘密とは何か?
翔子がカウンセリングを受けている間に、諒一と由香は結ばれてしまう。もちろん翔子は不幸のどん底に突き落とされる。
しかし冷静に考えれば、諒一と由香は一度セックスしただけなのだ。しかし自分の方は何十人という見知らぬ男と体を重ねて来た。罪深いのは私の方ではないかと翔子は自分を責める。
カウンセリングの女医が、秘密を解き明かしてくれる。ナラトロジーで言えばこの女医が「助言者」の役割を担っている。
翔子は幼い頃から意識下で親友の由香を母親の代役にして来たのだ、と女医は指摘する。由香はその代理役を長きにわたって引き受けて来た。由香という唯一無二の親友は、翔子の母親でもあったのだ。
そして由香と同じような家庭環境で育ったに違いない諒一は、懸命に翔子の保護者──すなわち父親になろうとして来た。
こうして、「擬似家族の形成」が成立してしまったのである。父親である諒一はネットで知り合った未知の男達のように、翔子を性の対象にすることなど不可能だった。翔子が必死に「求めて欲しい」と願っても、そんなことは不可能だったのだ。
しかし諒一は男としても翔子に愛されたいという葛藤があり、引き裂かれてしまった。その傷ついた心を癒やしてくれるのは由香しかいなかった。
子供としての翔子の存在そのものが、同じ子供を持つ夫婦のような関係を二人に与えてしまったのであり、だから彼らが結ばれるのは自然なことだった。
そしてこの女医は翔子に的確なアドバイスをするのである。
「あなたが今取り戻さなければならないものは、自分自身と、お母様との健全な関係です。彼と由香さんのことは少し距離を置きましょう」
この後は、初期の三島由紀夫の長編のような明確な構造を持ちながら展開していく。
この後は、是非ともご自分でお読みください。
一つだけ補足があるとすれば、中盤で翔子をもっとも深く傷つけた存在が、この物語の結末で他のものに代え難い美しい希望になるということだ。
物語という表現形式の、光り輝くパラドックスである。
ジェノバの夜を巡る長いレポートがこの作品なのであり、七井さんだけではなく僕ら全員が発表するしないはともかくレポートを書くべきなのである。
【「私」探しの旅の途上で】
このサロンを始める時に、僕は「私」探しの旅にもっとも有効な方法は物語の構造を明らかにすることであり、出来れば小説を書いてみることだと述べた。
覚えてますか?
いい小説を書いてお金を儲けることが目的なのではない。この地上で最も不可思議で魅力的な「私」という物語を深く理解するためにこそ、僕らは小説を書くのである。
藤沢周平の小説はゲゼルシャフト・メイキングである。主人公はたとえばあまり身分の高くないしがない侍である。毎日勤めに出かけ、短調な仕事をこなし、家に帰る。家では自分の稼ぎが良くないために、妻が内職をしている。
これだけのキャラクター・メイキングで小説を書くのは実は大変だ。しかしこの主人公にジェノバの夜が訪れたらどうなるだろうか? 主人公は藩から、親友を暗殺することを命令される。絶対にそんなことはしたくないが、断れば自分の命がない。
こうなって初めて、藤沢周平ワールドが展開していくのだ。『隠し剣鬼の爪』は、主人公のジェノバの夜そのものが秘剣に昇華しているところに読者は感動するのである。
ジェノバの夜は必須なのだ。
次回からは1つ1つの手法を詳しく解説していく。「神のデザイン」の解説では有島武郎の『カインの末裔』を扱いますので、時間がある方は読んでおいてください。
ご興味をお持ちの方は、ぜひオンラインサロンへご参加ください。