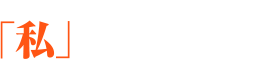特別公開:鬼に堕ちてしまうような痛みがなければ『鬼滅の刃』は成立しない2──ポストモダンや意識を追う小説よりも遥かに新しい世界 山川健一
現代文学の今のところの到達点はポストモダンだろう。だがそれが行き詰まり、文学が停滞しているわけだ。絵画の世界でも、いきなり抽象画が生まれたわけではなく、論理的な脈絡の中で抽象絵画が登場したように、ポストモダンも論理的な必然として生み出された小説の1つの形式である。
ピカソは突然変異として登場したのではなく、ポストモダンも同様だ。
小説ではなく漫画だが、たとえば…
—
次代のプロ作家を育てるオンラインサロン『「私」物語化計画』会員用Facebookグループ内の講義を、一部公開いたします。
ご興味をお持ちの方は、ぜひオンラインサロンへご参加ください。

→ 毎週配信、山川健一の講義一覧
→ 参加者募集中→ 参加申し込みフォーム
「私」物語化計画 2020年4月3日
特別公開:鬼に堕ちてしまうような痛みがなければ『鬼滅の刃』は成立しない2──ポストモダンや意識を追う小説よりも遥かに新しい世界 山川健一
現代文学の今のところの到達点はポストモダンだろう。だがそれが行き詰まり、文学が停滞しているわけだ。絵画の世界でも、いきなり抽象画が生まれたわけではなく、論理的な脈絡の中で抽象絵画が登場したように、ポスト
モダンも論理的な必然として生み出された小説の1つの形式である。
ピカソは突然変異として登場したのではなく、ポストモダンも同様だ。
小説ではなく漫画だが、たとえば『鬼滅の刃』はそれへの苛烈な揺り戻し現象なのだと思う。前回は、「ワールドモデル」と「キャラクター・メイキング」は不可分な関係があり、そのどちらもが「虫歯の痛み」のようなものを内包しているのだということを『鬼滅の刃』を題材に書いた。その続きを今週は書こうと思うが、その前に文学史と言うか、小説の書き方の歴史を振り返っておく。『鬼滅の刃』がいかに新しいかと言うことを理解して頂くためだ。
【作家論──意識を追う小説】
簡単に明治維新以降の文学の流れを振り返ってみる。
明治時代に日本では急速な近代化が行われた。言文一致運動というものがあり、文語からわれわれがいま普通に使っている言葉で小説も書かれるべきだ──ということになった。夏目漱石や森鴎外、二葉亭四迷などが「意識」というものにこだわり、それまでの日本文学とはちがった「小説」というものを書きはじめたのである。
こうした近代文学を対象に、やがて批評というものが生まれる。批評は文学に「意識」と言うものを明確に持ち込み、それが文学の主流になっていく。
僕は高校生の頃、小林秀雄の本を読むことで文学の勉強をした。なにげなく手にした小林秀雄の本を読んで唖然としたのだった。これが文学というものか──と、一種のショック状態だった。
ただし小林秀雄の批評の方法は非常に真面目で、考えてみればシンプルで簡単なものだった。ある作家を批評しようと思ったら、その作家の作品を年代順にすべて読めばいいのだ、と小林は書いている。
で、僕は当の小林秀雄の本を可能な限り手に入れて、最初の作品から順番にすべて読んだ。小林はできれば日記や書簡(手紙)も読めと言っていたので、僕はそうした。
すると、どういうことが起こると思いますか?
小林秀雄のことがよくわかるようになったのです。
ドスエフスキーも太宰治も横光利一も、谷崎潤一郎も、吉本隆明や江藤淳もそんなふうに読んだ。ゴッホやモーツァルトの書簡集も読んだ。
すると、彼らのことがよくわかるようになり、その作品が名作か駄作かということなどどうでもよくなる。出来の悪い子ほど可愛いと言うが、彼らの失敗作の中にこそ、かえって裸の作家の魂が垣間見えたりするものだ。三島由紀夫の最大の失敗作は『暁の寺』だと思うが、この作品が僕には愛おしい。
時はあたかも、高度経済成長の時代だった。
団塊の世代の子供達が大学に進学するようになり、女子の比率も飛躍的に拡大した。文学部というものが、そういう大勢の大学入学希望者の受け皿になった。知識人と言われる小説家達の作品を、1冊目から順番にすべて読むと、知識ばかりか人格的にも成長することができる──そういう暗黙の了解が大学関係者や父兄、それから学生自身にもあったのだろう。かくして文学部は大繁盛し、今では「そんなはずはないだろう」と多くの人達が気がつき、結果的に没落した。
【テキスト論で書かれた小説】
小林秀雄は「作家自身を理解することこそが大事なのであり、作品の出来不出来などどうでもいい」と公言していた。三島由紀夫もこれに倣った。しかしそんなことではそもそも批評というものが成立しないではないか、ということになってくる。
テキスト論(作品論)が登場したのである。
ロラン・バルトの「作家は死んだ」と言う宣言が有名だが──煩雑になるので詳細は省く。
テキスト論というのは、ある小説を読む場合、作品を作家から完全に切り離して読むことが可能だ、という立場である。そこでは小説家は人格者である必要も知識人である必要もなく、問題なのはテキスト(小説)だけなのだ。これで、哲学・思想・文学の世界は大きく変わっていく。
文学の世界では、作家論→作品論→構造主義の登場による価値の相対化→ニューアカデミズムによる単一的な価値の否定→そして遂に、ポスト構造主義(ポストモダン)による「世界は言語でできている」という結論に至る。
ポストモダン小説とは、乱暴なまとめ方かもしれないが「私には特別な体験もなく、私は特別な人間ではない」
「私にはもう固有な感動などない」「すべての感動を過去の作家が私よりも上手に書いてしまっている」「私がこれに付け加えることなど何もない」「せめて引用するぐらいが関の山だ」「感動を引用するなら組み合わせが大切だ」──と言うようなことになるのではないだろうか。
そして、今。
今日の時代論は来週から書こうと思うが、世界は破滅的な危機に陥っている。新型コロナウィルスの問題だけではなく、経済格差や地球環境の引き返すことができない悪化が人間を追い詰めている。
そんな今「私にはもう固有な感動などない」「すべての感動を過去の作家が私よりも上手に書いてしまっている」などと言っていては「寝言は寝て言え」と読者から罵声を浴びせられてしまうだろう。ま、仰る通りである。
こうして、文学や思想の世界も日本という国家もメチャクチャになってしまい、作家論かテキスト論かという以前に、文学そのものの力が弱りきってしまったのだ。日本という国家が溶解しそうで、そんな時にどんな作品を構築すればいいのだろうか?
【大正時代を舞台にした『鬼滅の刃』の新しさ】
『鬼滅の刃』と言う作品には、まず作者の表現したいこと、意図がある。
作者の隠された意図とは例えば──続きはオンラインサロンでご覧ください)