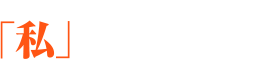特別公開:発語の不可能性を乗り超えるために3 ヘンリー・ミラー『北回帰線』を読む 山川健一
「小説という器には、様々なものを入れることができる。野菜や肉を入れて煮込み、カレーを作るようなものだ。小説における玉ねぎやニンジン、ジャガイモや肉にはどんなものがあるだろうか。
まず、読者が楽しむことができるストーリーをあげなければならない。ただしストーリーを描くだけではあらすじになってしまうので、情景描写も必要だ。その他にも、身体性、哲学や思想、最新の科学の知見、愛とセックス、歴史や心理学や政治的なスタンス──なども盛り込むことが出来る」
次代のプロ作家を育てるオンラインサロン『「私」物語化計画』会員用Facebookグループ内の講義を、一部公開いたします。
ご興味をお持ちの方は、ぜひオンラインサロンへご参加ください。

→ 毎週配信、山川健一の講義一覧
→ 参加者募集中→ 参加申し込みフォーム
「私」物語化計画 2019年11月22日
特別公開:発語の不可能性を乗り超えるために3 ヘンリー・ミラー『北回帰線』を読む 山川健一
小説という器には、様々なものを入れることができる。野菜や肉を入れて煮込み、カレーを作るようなものだ。小説における玉ねぎやニンジン、ジャガイモや肉にはどんなものがあるだろうか。
まず、読者が楽しむことができるストーリーをあげなければならない。ただしストーリーを描くだけではあらすじになってしまうので、情景描写も必要だ。その他にも、身体性、哲学や思想、最新の科学の知見、愛とセックス、歴史や心理学や政治的なスタンス──なども盛り込むことが出来る。
今週は「書き出し」「発語」について考えるのだが、大切な事は、小説の冒頭部分で作家はカレーを作る鍋を用意しなければならない、ということだ。あなたがこれから作ろうとするカレーに最適の鍋が用意できれば、後は好きな材料をぶち込めばいいだけだ。
玉ねぎ、ニンジン、ジャガイモ、牛肉──おっと、僕はポークカレーの方が好きなのでここは豚肉。そういえば昨夜半分だけ食べたりんごが余っていたな、ということで半分のりんごも入れてしまおう。
そんなオリジナルな「鍋」を冒頭で作る方法を、ヘンリー・ミラーに学ぼう。
まずヘンリー・ミラーという作家の横顔解説を試みます。
ヘンリー・ミラーの二番目の妻だったジューンは、ミラーの作家としての才能を信じて疑わなかった。ニューヨークでの暮らしを高級娼婦をやりながら支え、ドラッグや酒をやり、ジーン・クロンスキーというレズビアンの恋人もいた。この妻の恋人から、ミラーはランボーを教えられるのだ。
この三角関係を描いたのが『クレイジー・コック』である。ジューンはニューヨークの出版社を回り、なんとか『クレイジー・コック』を出版しようとするが、これは叶わなかった。
「なんとかなるかもしれない。うまくいくと思う」と、ジューンはミラーに可愛らしい嘘をつきつづける。
不可思議な三角関係に疲れたミラーは、西海岸へ放浪の旅に出る。旅先で無政府主義者エマ・ゴールドマンと知り合い、しかしアナーキズムではなくドストエフスキーを教えられた。
ランボーとドストエフスキーの前では、自分が最初に書いた長編『クレイジー・コック』はいかにもみすぼらしく見えた。それでこの本を出版する情熱をミラー自身が失ってしまうのだ。
ミラーは、詩の最高峰としてのランボー、散文の最高峰としてのドストエフスキーに挟まれ、発語の不可能性に苦しむことになる。つまり1行も書けないのである。
ミラーとジューンはその後パリに行く。ヘミングウェイやフィッツジェラルドがパリにいた10年後ぐらい、1930年代のことである。
ミラーはパリでルイ=フェルディナン・セリーヌの存在を知る。『夜の果ての旅』(中公文庫/訳・生田耕作)の作家である。セリーヌから、ミラーは世界を罵る言葉の数々を学習した。
あるいは、小説というものは自分が考えていたような形式なんて放棄してしまってもいいのだという、自由の感覚を手に入れた。むしろそのほうが、ドストエフスキーやランボーを追いつめることができるのだ、ということを知ったのだろう。
たとえばミラーは、初期作品を三人称で書いている。いかにもこれは小説ですというような、三人称、つまり「彼は……」とか「トニー・ブリングは……」というような書き方をしている。だが『北回帰線』は一人称で書かれている。それは、ミラーの勝利であった。一人称で自由に書かなければ、あのようにセックスの描写と哲学的な思索が自由に混在するようなミラーの世界は生まれようがなかったのである。
ところで、ミラー自身は、ランボーやセリーヌに比べ、遥かに素朴でポジティヴな資質をその内側に持っていた。あるいは、ランボーやセリーヌ以上に膨大な枚数を書き続けたからこそ、ミラーは明るい場所に出ることができた、と考えるべきなのかもしれない。いずれにせよ、かくして、壮大なミラー世界が展開されることになったのだ。
ミラーはパリで銀行員の妻で作家のアナイス・ニンと出会い、ミラーとアナイス、ジューンの危険な三角関係が始まる。ミラーはアナイスに出版社を紹介してもらい『北回帰線』でデビューした。
この処女作が出版される直前、ジューンは離婚してミラーの元を去った。
もしもアナイス・ニンの助力による『北回帰線』より先に、ジューンの売り込みで『クレイジー・コック』がニューヨークで出版さていたら、ヘンリーとジューンの運命は変わったかもしれないなと僕は思うのだ。しかし、やはり傑作『北回帰線』こそがミラーのデビュー作であるべきだったのだろう。
ヘンリー・ミラーはそれから、ほぼすべての長編小説でジューンへの愛を書きつづけた。性器の奥にある子宮そのもののような愛──しかしその子宮はミラーにとって、もうここにはない、失われたものだったのである。「私はファックの国の住人だ」と言い放ったミラーの、それこそが本心だった。
晩年のジューンは不幸だった。『北回帰線』はアメリカでは発禁処分で、生涯を通してお金には恵まれなかったミラーだが、それでも小額の小切手をジューンに送りつづけた。ジューンは最終的には精神病院に収容されてしまう。
ジューンは2つのトランクを、肌身離さず持っていた。じつはこのトランクの1つに、ミラーの幻の処女作「モロク」と「クレイジー・コック」の原稿が入っており、彼女は決してそれを手放そうとはしなかったのである。
それこそは、ジューンが体現し得る至上の愛というものだったのではないだろうか。
さて、それでは発語の不可能性に苦しんだヘンリー・ミラーがようやくのことで書き出したデビュー作『北回帰線』の冒頭部分を読んでいこう。僕の解説を【】で示すことにするが、まずは解説なしで読んで下さい。
北回帰線(冒頭部分) ヘンリー・ミラー
ぼくはヴィラ・ボルゲエゼに住んでいる。ここには塵っぱひとつなく、椅子の置場所ひとつまちがっていない。ここでは、ぼくたちはみな孤独であり、生気をうしなっている。
昨夜ボリスは、からだに虱がたかっているのに気づいた。ぼくは彼の腕の下を剃ってやらなければならなかったが、それでもまだ痒みはとれなかった。こんなきれいなところにいて、どうして虱なんぞにたかられるのか。だが、そんなことはどうでもいい。ボリスとぼくとは、もし虱がいなかったら、これほど仲好くはならなかったかもしれないのだ。ボリスは、やっと一通り、彼の意見の概要をぼくに語ってくれたところだ。彼は天気予報の名人である。この悪天候はまだつづくだろう、と彼はいう。天災や、死や、絶望が、まだまだつづくだろう。どこにも毛筋ほども好転の兆は見られない。時間の癌腫が、おれたちを食いほろぼしつつある。おれたちの主人公たちはみな自殺してしまったか、または現に自殺しかけている。してみれば主人公は「時間」ではなくて「無時間」にほかならない。おれたちは目白押しにならんで死の牢獄にむかって行進して行かねばならないのだ。逃げ路はどこにもない。天気は変るまい。
パリへきてから、もう二度目の秋だ。ぼくは、いまだに推察できずにいるある理由から、この土地へ追いやられてきたのである。ぼくは金がない。資力もない。希望もない。ぼくはこの世でいらばん幸福な人間だ。一年前、半年前には、自分を芸術家だと思っていた。いまでは、そんなことには頭をつかわない──ぼくは存在するだけだ。かつて文学であったもののことごとくが、ぼくから脱け落ちてしまった。本に書くことなど、もう一つとしてない。ありがたいことだ。
ではこれは何だ? これは小説ではない。これは罵倒であり、讒謗であり、人格の毀損だ。言葉の普通の意味で、これは小説ではない。そうだ、これは引きのばされた侮辱、「芸術」の面に吐きかけた唾のかたまり、神、人間、運命、時間、愛、美……何でもいい、とにかくそういったものを蹴とばし拒絶することだ。ぼくは諸君のために歌おうとしている。すこしは調子がはずれるかもしれないが、とにかく歌うつもりだ。諸君が泣きごとを言っているひまに、ぼくは歌う。諸君の汚ならしい死骸の上で踊ってやる。
歌うからには、まずロを開かなければならぬ。一対の肺と、いくらかの音楽の知識がなければならぬ。かならずしもアコーディオンやギターなんぞなくてもいい。大切なことは歌いたい欲求だ。そうすると、それが歌なのだ。ぼくは歌っているのだ。
おれはおまえに向って歌っているのだよ、タニア、おまえに向って。できることなら、もうすこし上手に、もうすこしうるわしい調子で歌いたいのだが、それだと、おまえはきっとおれの歌を聞いてくれる気にならないだろう。おまえは他の奴らの歌うのを聞いた。だが興冷めしてしまった。奴らは、あまりに見事に歌いすぎたか、見事さが足りなかったか、そのどちらかだ。
今日は十月の二十何日かだ。ぼくはもう日付もわからなくなっている。去年の十一月十四日のぼくの夢はどうだったか──と諸君はいうのか? 時間のヘだたりはあるが、それは夢と夢とのあいだのヘだたりであり、夢は意識に残っていない。ぼくをとりまく世界は、あちこちに時間の汚点を残して消滅しかかっている。世界は、みずからを食いほろぼす癌なのだ……大きな沈黙が、すべての上に、あらゆる場所に落ちかかるとき、音楽は、ついに凱歌をあげるだろう、とぼくは考えている。時間の子宮のなかへ、すべてのものが、ふたたび退き去るとき、ふたたび混沌があらわれるだろう。混沌こそは、その上に真実の書かるべき楽譜である。タニアよ、おまえはおれの混沌なのだ。おれが歌うのもそのためだ。時間の皮を剥ぎ落すのは、おれですらない。それは死にかけている世界なのだ。おれはおまえの子宮のなかへ書くべき真実を蹴こみながら、こうしてまだ生きている。まどろみ。恋愛の生理学。興奮していないときでも六フィートのぺニスをもっている鯨。遊動ぺニス。ぺニスに骨のある動物。骨があるから突張るのだ。「さいわいなことに」とグゥルモソはいう、「この骨は人間にはうしなわれている。」さいわいなことに? そうだ、さいわいなことにだ。ベニスを突張らせて歩いている人間を考えてみるがいい。カンガルーは二叉のペニスをもっている──一本はウィーク・デー用であり、一本が休日用である。ねむい。ある女から手紙で、ぼくの本の標題がきまったかとたずねてきた。標題だって? きまったさ──『美しき同性愛の女たち』というのだ。
──『北回帰線』冒頭部分(大久保康雄訳/新潮文庫)より引用
それでは【】僕の解説をつけたバージョンを読んでみてください…..,(特別公開はここまで、続きはオンラインサロンでご覧ください)