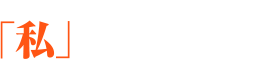冬の特別配信:スピカと月 2/3 山川健一
そんな悲観的な男は、未希子に限らず、誰かといっしょに暮らす資格などないのかもしれない──
次代のプロ作家を育てるオンラインサロン『「私」物語化計画』会員用Facebookグループ内の講義を、一部公開いたします。
ご興味をお持ちの方は、ぜひオンラインサロンへご参加ください。

→ 毎週配信、山川健一の講義一覧
→ 参加者募集中→ 参加申し込みフォーム
「私」物語化計画 2021年12月17日
冬の特別配信:山川健一『スピカと月』(2/3)
運営事務局より〜年末を迎えるにあたり、12月10日、17日、24日の3週にわたり、山川健一の小説を一部掲載いたします。
冬の特別配信
スピカと月 2/3
山川健一
車をパーキングに入れ、ぼくは2CVを振り返った。ラジエター・グリルが動物の口のようなこの車は愛嬌があった。すると、黒く塗られたフェンダーは、ちょうど頰にあたることになる。この車が単なる機械だなんて、今のぼくには信じられない。
ぼくらは運河沿いの道を歩いていった。相変わらず雨が降っていたが、車を降り駅前の広場に立った時に、潮の匂いの中に遅い春の気配を感じることができた。北国のこの町でも、氷の季節はもう終わったのだ。
札幌での会議が思いのほか早い時刻に終了し、小樽まで足を延ばしてみる気になった。未希子の提案だった。以前と少しも変わらぬ俊敏さで、彼女は札幌のホテルをキャンセルし、小樽の一風変わったホテルの部屋をリザーブした。ホテルやクッキーやアクセサリーや、そんな物を選ぶ彼女の目はいつでもぼくより遥かに正確なのだ。
ウィンドウに飾られたガラスの工芸品の前で、未希子は何度も足を止め、その度にぼくは未希子のペイズリー柄の傘越しに、ピンクのマドラーや濃い青の紅茶カップを眺めたものだった。ぼくはまだ迷っていた。スーツの内ポケットの中にしまったプレゼントをどんなふうに彼女に手渡すか迷っていた。そして、今のこの季節のように温もりはじめようとする心を諫めるのだった。
運河にぶつかり、通りを右に折れる。運河にも雨の雫が落ちている。初めての町なのに、不思議に懐かしい感じがした。古い倉庫が運河に面して立ち並んでいた。未希子は自分の傘をたたみ、ぼくの傘の中に入ってくる。ぼくのコートのポケットに、腕でも組むように手を入れて歩いた。
そんなふうに未希子と歩いていると、札幌の会議に出席した時に入手した、地球の気象が狂いはじめていることを示すさまざまなデータがゆっくりと消えていく気がした。
ぼくは商社に勤務している。穀物や果物や乳製品をはじめ、いろいろな食料品の輸入も行っている。そんな商社にとって、気象をめぐる会議でデータを収集するのはきわめて重要な仕事のひとつだった。気象は、世界の食糧事情を左右しているのだ。そして世界の経済の鍵を握っているのはもはや石油ではなく、食糧だった。いずれにせよ、どんな事態になろうと、商社は有効に機能するだろう。そして、自分はいつでもそれを支えようとするだろう。
「ねえ、なにを考えているの。会議のこと?」
「まあね」
「あなたは、いろいろなことを真剣に考えすぎるのよ。それで悪夢にうなされるんだわ」
未希子がそう言った。ぼくは、煙草に火をつける。一服してから、なにか言おうとして、だが声がかすれてしまう。
ひとつ咳をしてから、ぼくは言った。
「悪夢ではなくて、現実なんだよ」
仕事の一環として気象のデータを集めるようになってから、ぼくは地球の未来に絶望している。人類は、もちろん賢明な生き物だった。だが、十分に賢明ではなかった。そのことが、愚かであるよりも始末の悪い結末を自分自身に用意しそうなのだ。
ぶ厚い雲の向こうの太陽は傾いてしまった。町のあちこちに街灯が灯されはじめる。旅の途中の狂った一日が、今日もまた終わろうとしているのだ。
やがて、大正時代に建てられた銀行を改造したホテルが見えてきた。
「どう?」と未希子。
「うん」
「わたし、一度来てみたかったのよ」
ぼくらは立ち止まり、しばらく異国の街角に建ったような、そのホテルを眺めていた。
既に十分過ぎるほど眩しい光。
ゆっくり目を開くと、レースのカーテンの向こうに太陽の光が輝いている。昨夜の雨が噓のようだった。部屋の隅に置かれた品のいい小さなサイドテーブルの上に、シェリーが三分の一ほどのこった細長いグラスが見えた。昨夜は遅くまで、エジプトを思い出させるこの部屋で酒を飲み、愛し合い……ぼくはその時初めて、隣りに未希子がいないことに気がついた──続きはオンラインサロンでご覧ください)