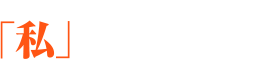冬の特別配信:スピカと月 1/3 山川健一
未希子は黙ってうなずき、ぼくの手を強く握り返してきた。わたしはいつもあなたの側にいるのよ、とでも言うように──
次代のプロ作家を育てるオンラインサロン『「私」物語化計画』会員用Facebookグループ内の講義を、一部公開いたします。
ご興味をお持ちの方は、ぜひオンラインサロンへご参加ください。

→ 毎週配信、山川健一の講義一覧
→ 参加者募集中→ 参加申し込みフォーム
「私」物語化計画 2021年12月10日
冬の特別配信:山川健一『スピカと月』(1/3)
運営事務局より〜年末を迎えるにあたり、12月10日、17日、24日の3週にわたり、山川健一の小説を一部掲載いたします。
冬の特別配信
スピカと月 1/3
山川健一
東京─札幌間の便が空港に着いた時、氷のような雨が降っていた。
金曜日の朝だった。
飛行機の丸い小さな窓から見上げる空はぶ厚い雲で覆われ、離陸のため待機している旅客機の赤いランプが、雨に濡れた滑走路にぼんやりした光の影を落としていた。ようやく未希子に会えるのだ、と思った。
もう十数年前、初めて北海道にやってきた時のことを思い出す。
未希子と二人で乗ったフェリーボートが港に着いた時、もう春だというのに雪が降っていた。カモメ達が海面すれすれを飛んでいた。
免許を取ったばかりのぼくは、凍った道をうまく運転できるかどうか、心配していた。未希子のほうは札幌の出身で雪道など慣れたものだったが、その頃はまだ免許を持っていなかったのだ。しかも、当時のぼくが初めて手に入れたその車は、時速六〇kmで走るとボディが分解してしまいそうな勢いで激しく震動するシトローエン2CVだった。きっとホイールバランスが狂っていたのだろうと思う。ぼくが当時フランス文学の勉強をしていることを知った友人の父親が、安く譲ってくれた車だった。
フランスの車だというので期待に胸を膨らませて友人宅に出向いたのだが、そのエスカルゴみたいな奇妙なスタイルの車を見た瞬間、膨らんでいた期待は針で突かれた風船みたいに、みごとに萎んでいった。
「……この車は、ブリキでできているんですか?」
悪気はなかったのだが、ぼくは高校の校長を務めているという友人の父親にそう聞き、彼は苦笑しながらこんなふうに答えたものだった。
「君、こいつは名車なんだよ。乗ればわかる。こいつに乗れば、フランス人の文学ってものが、頭ではなく、肉体と心で理解できるようになるさ」
それから彼は2CVが登場する映画のタイトルを順番にあげていったが、ぼくはもうそんな彼の話を聞いてはいなかった。
初めて北海道の雪道を走りながら、ぼくは不安の塊になっていき、そんなぼくを未希子は励ましつづけた。
未希子はあの頃、いつでもぼくを励ましていたように思う。凍った道を運転しなければならない時にも、そして、フランスの現代小説に関する卒業論文を書く時にも。
ほどよく暖められた通路を歩き、空港ロビーに出る。小振りの革のスーツケースを受け取り、外に出る。人込みの中で、小さく手を振っている未希子が見えた。懐かしさが込み上げてきて、もう大人だというのに鼓動が速くなってくるのがわかる。いつでも夜になる度に隣りで眠りたいと思い、だがいつもは、月の彼方ほど遠いところにいる未希子。
「いらっしゃい」
未希子は少しばかり首を右に傾け、とても自然に微笑んでいた──続きはオンラインサロンでご覧ください)