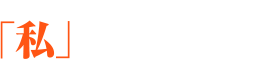特別公開:小説の終わらせ方 03 喪失感の表現で終わらせる。 山川健一
多くの作家たちは「喪失感」の表現を巧みに磨いて来た。恐怖や苦痛を内包した悲しみの感情を描くことで作品を終わらせてきたのである──
—
次代のプロ作家を育てるオンラインサロン『「私」物語化計画』会員用Facebookグループ内の講義を、一部公開いたします。
ご興味をお持ちの方は、ぜひオンラインサロンへご参加ください。

→ 毎週配信、山川健一の講義一覧
→ 参加者募集中→ 参加申し込みフォーム
「私」物語化計画 2021年4月30日
特別公開:小説の終わらせ方 03 喪失感の表現で終わらせる。 山川健一
すべての物語は、主人公である少年や少女が、いくつかのイニシエーションを経て大人になっていく過程を描くものである。つまり、成長する。だが成長するという事は、必ずしもポジティブな側面ばかりを持っているわけではない。人間は生まれ、体は成長していき、言葉を学び、言葉によって世界について知見を深めていくことで、大人になる。
しかしその間にも、刻一刻と「死」に近づいていくのである。人間をはじめ多くの生命は、有限の時間を与えられ、その短い時間を生きるしかない。
どうせ老いて死ぬのなら、なぜ努力しなければならないのか。世界に関する知見などどうでもいい話で、その時々の「今」だけを見て生きればいい。「死」が恐怖と苦しみを与えるのは必定で、だったら努力など無駄なことではないのか。
COVID-19による死者の数が、日本ではついに1万人を超えてしまった。僕らの周囲は今、死の恐怖に満ちているのだ。
それでも僕らは努力する。世界というものに、一方的な片想いをし続ける。
なぜだろう?
個人は死んでも種としての人類は続くからだろうか。自分の子供達がバトンを受け継ぐからか。しかしその子供たちだって、僕らと同じようにやがて死ぬしかないのである。
物語は、こうした事情の上に成立している。
どんなに血湧き肉躍る冒険物語でも、その主人公は死の恐怖と苦痛から逃れることはできない。しかしそれをレアな状態で書いてしまうと物語を終えることができないので、多くの作家たちは「喪失感」の表現を巧みに磨いて来た。恐怖や苦痛を内包した悲しみの感情を描くことで作品を終わらせてきたのである。
壮大な物語でも小さな小説でも事情は同じだ。
今回もまた、具体例を挙げながら説明していきたい。
【川上弘美『センセイの鞄』】
川上弘美さんの『センセイの鞄』は恋愛小説である。2001年度の谷崎潤一郎賞の受賞作品だ。映画化もされ、純文学としては異例の15万部超のベストセラーとなった。
主人公のツキコさんこと大町月子は行きつけの居酒屋で、30歳離れた高校の恩師で古文の先生だった、「センセイ」こと松本春綱に再会する。センセイが「ツキコさん、デートをいたしましょう」と言うことから2人の恋愛が始まる。ツキコさんは37歳、センセイは67歳である。
2人は露店めぐりやお花見へ出かけ、時にささいな喧嘩もしながら、ゆたかに四季をめぐっていく。飄々としなら、やがて慈しみあうようになる。
2人はセンセイの亡き妻のお墓参りに行ったり、美術館に出かけてたりする。センセイは体の結びつきが恋愛には大切だと考えているのだが、そういうことをする自信がない。老いのせいだ。
この小説の恋愛は、どんな場面でも「老い」と「死」を背景にしている。
美術館に行ったシーンを引用する。
「ツキコさん、ワタクシはいったいあと、どのくらい生きられるでしょう」
突然、センセイが聞いた。センセイと、目が合った。静かな目の色。
「ずっと、ずっとです」わたしは反射的に叫んだ。隣のベンチに座っている若い男女が驚いてふり向いた。鳩が何羽か、空中に舞い上がる。
「そうもいきませんでしょう」
「でも、ずっと、です」
センセイの右手がわたしの左手をとった。センセイの乾いたてのひらに、わたしのてのひらを包むようにする。
「ずっと、でなければ、ツキコさんは満足しませんでしょうか」
え、とわたしは口を半びらきにした。センセイは自分のことをぐずだと言ったが、ぐずなのはわたしの方だ。こういう話をしているときなのに、しまりなく半びらきになるわたしの可哀相なロ。
いつの間にか母子は姿を消していた。日が暮れかかっている。闇の気配が薄く薄くしのびよろうとしていた。
「ツキコさん」と言いながら、センセイが左手のひとさし指の先っぽを、わたしのひらいた口の中にひゅっとさし入れた。仰天して、わたしは反射的に口を閉じた。センセイはわたしの歯の間にはさまれる前に、素早く指を引き抜いた。
「何するんですかっ」わたしはふたたび叫んだ。センセイはくすくす笑った。
「だって、ツキコさんがあんまりぼうっとしているから」
「センセイが言ったことを真面目に考えてたんじゃありませんか」
「ごめんなさいね」
ごめんなさいね、と言いながら、センセイはわたしを抱き寄せた。
抱き寄せられたとたんに、時間が止まってしまったような感じがした。
センセイ、とわたしはささやいた。ツキコさん、とセンセイもささやいた。
「センセイ、センセイが今すぐ死んじゃっても、わたし、いいんです。我慢します」そう言いながら、わたしはセンセイの胸に顔を押しつけた。
川上弘美『センセイの鞄』
恋愛という生命の讃歌を描きながら、老いと死を重ね合わせる。死について語った後、女の口に指を入れるという、ユーモラスでもあり官能的でもある動作を差し込む。巧みと言うしかない。
やがてセンセイは亡くなり、センセイの息子さんから鞄を形見にもらった。「父春綱が生前にお世話になったそうで」と息子さんは頭をさげる。春綱というセンセイの名を聞いて、ツキコさんは涙があふれそうになる。
この小説の結末部分───続きはオンラインサロンでご覧ください)