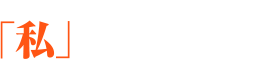特別公開:特別編・長い小説を書くために2 「エリナー・リグビー」に登場する全ての孤独な人々 山川健一
年齢を重ねて行き、30歳の壁を超え、40歳の壁を超え、さらに50歳を超えてもなおかつ新鮮な作品を書き続けるコツは何だろうか?──
—
次代のプロ作家を育てるオンラインサロン『「私」物語化計画』会員用Facebookグループ内の講義を、一部公開いたします。
ご興味をお持ちの方は、ぜひオンラインサロンへご参加ください。

→ 毎週配信、山川健一の講義一覧
→ 参加者募集中→ 参加申し込みフォーム
「私」物語化計画 2020年10月2日
特別公開:特別編・長い小説を書くために1 ジュネットの焦点化から学ぶ 山川健一
今回もキャラクターメイキングをお休みし、緊急特別編として、創作技法について述べる。先週予告しておいたように、ビートルズの「エリナー・リグビー」を素材にします。
Eleanor Rigby – PAUL McCARTNEY – YouTube
【年齢の壁を超える】
ジュネットの焦点化の話は難しかったようで、質問のメールが何通が届いた。
代表的なのはこんなメールです
「内的焦点化を徹底する=主人公を勁くする」とはどういうことなのでしょうか? 水彩画のスケッチのように曖昧さを残したまま進むのではなくて、欲望や欠落を明確に設定しろということでしょうか。
これはもっと単純な問題です。
ジュネットは、焦点化を3つに分けた。
「1. 焦点化ゼロ(非焦点化)」、「2. 内的焦点化」、「3. 外的焦点化」だ。
このうち、内的焦点化とは、ある登場人物を「視点人物」に設定し、この人物によって知覚された事柄だけを描く方法だ。
人称は1人称でも3人称でも可能だが、1人称の方が書きやすいだろう。
これは手紙と同じで、小説の技法としては最もプリミティブな、感情を表現しやすい形式だと言える。ジュネットが「焦点化」という言葉を使ったのは、もう少し俯瞰的な視野があったからだろうが、実作者の皆さんはあまり気にしなくても良い。
皆さんに理解して欲しいのは、小説の基本は「内的焦点化」だということだ。小説というものはありもしない嘘っぱちをあたかも本当の出来事のように読者に伝える表現形式だ。そのためには、主人公の感情が強く表現されなければならない。
これを実現するためには「内的焦点化」を徹底させるのが最も良い。
100枚程度の作品ならこれで充分可能だろうが、小説が長くなり世界が拡大していくと、ある特定の人物の視点だけで全てを描くのは不可能になってくる。そこで会員のみなさんからも「1人称で書きたいのですが、章によって該当人物を変更してもいいですか?」というような質問が届く。
ドストエフスキーも、『罪と罰』の途中までは1人称による内的焦点化の方法論で書いていた。しかしそれではどうにも世界が拡大できなくなり、泣く泣く3人称に切り替えて作品を改稿していったのだ。
若い頃、米川正夫訳の全集の『罪と罰』に付いていた創作ノートでこの事実を発見した時、僕は感動したものだった。
したがって僕らも、可能な限り内的焦点化の方法で書き進めるのが良い。1人称で書いて、章が変わると同じ1人称だが語り手が変わるというパターンがよくあるが、これも可能な限り避けた方が良い。
なぜなら、どうせ嘘っぱちに過ぎない小説だからこそ、読者が自然に読んでいける方がいいに決まっているからだ。可能な限り自然な流れを断ち切らないことが大事だ。
引用したメールにある「内的焦点化を徹底する=主人公を勁くする」とは、可能な限り主人公の内面を表現していけば、主人公が勁くなる──という意味だ。
小説を書いていて、途中で構成が曖昧になったり、何を表現したいのか分からなくなってきたりすると、僕はよく自分に「主人公にもっとパワーを!」「こいつをもっとロックさせろ!」と言い聞かせる。
ただ問題なのは、この方法論は、若い頃でないと有効ではないということだ。人間は年齢を重ねるとともに、残念ながら強い感受性というものを失ってしまう。
先ごろ、女優の竹内結子さんが亡くなった。新型コロナによる自粛生活が多くの人を追い詰めているという分析があり、それはあるだろうなと思う。
僕は事情を全く知らないので軽はずみな事は言えないが、40歳という年齢の壁を越えることが困難だったのではないかと推察する。作家や脚本家や監督や、つまり肉体を人前にさらさない職業の方が、俳優や女優やシンガーなどに比べ、年齢の壁は越えやすいのだろうと思う。
しかしそれでも、小説を書きながら年齢の壁を越えていくのは、なかなかに大変なのだ。
【エリナー・リグビーの悲しみを持続させること】
年齢を重ねて行き、30歳の壁を超え、40歳の壁を超え、さらに50歳を超えてもなおかつ新鮮な作品を書き続けるコツは何だろうか?
それは、例えば19歳の頃の自分に流れていた悲しみを持続させること以外にない。
さて。
ビートルズの「エリナー・リグビー」は聴いて頂けただろうか。ポール・マッカートニーの歌い出しは、戦慄的な悲しみに満ちている。
何度聴いても、悲しみが溢れる。
「エリナー・リグビー」(Eleanor Rigby)は、ビートルズの楽曲であり、レノン=マッカートニー名義となっているが、ポール・マッカートニーの作品だ。ビートルズの場合、リードボーカルを担当している人がその曲を書いていることが多いのでわかりやすい。
コーラスにもジョン・レノンの名前がクレジットされているが、ほとんど聴き取ることができない。
1966年8月に「イエロー・サブマリン」との両A面シングルとして発売され、同時発売された7作目のイギリス盤オリジナル・アルバム『リボルバー』にも収録された。シングルは、全英シングルチャートで4週連続1位を獲得し、13週にわたってチャートインした。
ポールはまだ23歳だ。
ビートルズはロックバンドなのに、この曲にはギターもベースもドラムも入っていない。それまでにも弦楽四重奏がビートルズの演奏をバックアップすることがあったが、この曲は8つの弦楽器だけで演奏されている。
この頃ビートルズはライブ活動が不可能になり、前作『ラバー・ソウル』以上に、「ライヴで再現出来る曲作り」という縛りから解放され、スタジオでやれる事は全てやると言う方法論に貫かれている。
他の曲では、ジョンがテープに逆回転のボーカルを入れてたりしている。
「エリナー・リグビー」では弦楽器をベースのように使用したり、打楽器のような使い方をしたり、弦楽器の可能性を最大限に解放した結果この演奏が生まれた。
誰のアイディアなのかは不明だが、ポール自身の強いコンセプトがこの世界を生んだことに間違いは無い。
ロック衝動的な怒りを歌う──というそれまでのコンセプトから大きく外れた楽曲である。
小説を描く僕らは、歌詞の世界にも注目しなければならない。
この曲は──続きはオンラインサロンでご覧ください)