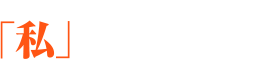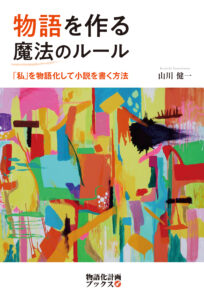キャラクター・メーキングで失敗しないために 03 文学上の原理、芸術の掟 山川健一
──この事実に気がついた時、僕は密かに戦慄し、太宰治の方法論を可能な限り自分から遠ざけようと努力した──
次代のプロ作家を育てるオンラインサロン『「私」物語化計画』会員用Facebookグループ内の講義を、一部公開いたします。
ご興味をお持ちの方は、ぜひオンラインサロンへご参加ください。
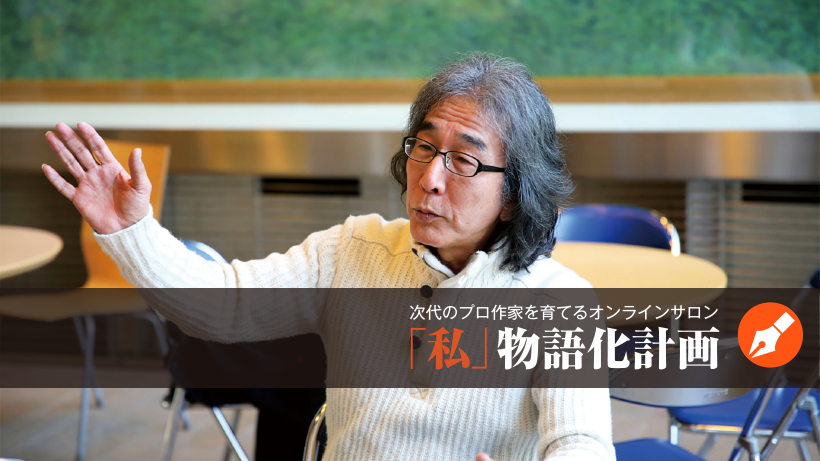
→ 毎週配信、山川健一の講義一覧
→ 参加者募集中→ 参加申し込みフォーム
2025年4月25日
特別公開:キャラクター・メーキングで失敗しないために 03 文学上の原理、芸術の掟 山川健一
【命懸けの冒険、それがキャラクター・メーキング】
多くの場合、小説の主人公はそれを書いた作家の半ば分身なのではないだろうか。とりわけ日本文学ではそうだった。
私小説になると、作家の側がこの原理を逆手に取り、必要以上に露悪的な作品も生まれた。
文は人なりという言葉を、多くの読者は信じていた。小説家は物語の提供者であるにとどまらず、総合的な知性人として振る舞っていたのだ。夏目漱石や森鴎外の時代の話である。
やがて近代的な概念が、文学の世界でも取り込まれるようになると、キャラクター・メーキングというものが意識的に考えられるようになった。谷崎潤一郎の『刺青』や三島由紀夫の『金閣寺』の主人公は、明らかに意図的に構築された存在であり、作家自身ではないだろう。
それでもなお、「彼」は谷崎的な人間であり、三島的な存在なのである。それを僕は、小説のキャラクターは作家の「私」が分割されたものだと考えているわけだ。
最近、物語化計画の木綿子さんが上梓する句集『カメリア手帳』(木綿子)に収録される俳句を読んでいる。
《古き夢息吹き返す朝の虹》
《悪夢見たシーツ洗ひて梅雨に入る》
こんな現代的な俳句を読みながら、僕は考えた。俳句や短歌におけるキャラクター・メーキングとはどのようなものなのだろうか、と。
悪夢を見たのは誰なのか?
それはおそらく「木綿子」さん自身なのだろう。そうしてみると、俳句や短歌は小説よりも作品と作者の距離が近いということになる。
小説においては、作品と作者の距離の取り方はなかなかに厄介である────続きはオンラインサロンでご覧ください)
山川健一
『物語を作る魔法のルール
「私」を物語化して小説を書く方法』
(物語化計画ブックス)Kindle版
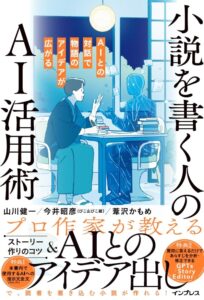 山川健一/今井昭彦/葦沢かもめ
山川健一/今井昭彦/葦沢かもめ
『AIとの対話で物語のアイデアが広がる
小説を書く人のAI活用術』(インプレス)
Amazon https://amzn.to/4dSXYLr
インプレス https://book.impress.co.jp/books/1124101059