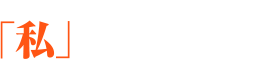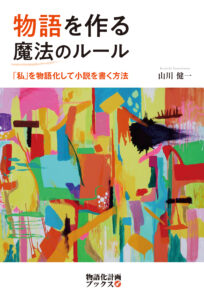キャラクター・メーキングで失敗しないために 02 大江健三郎『日常生活の冒険』における認識者と行為者の原理を学ぶ 山川健一
──キャラクター・メーキングする時、意図的に「認識者」と「行為者」を設定するのは有効な方法論の一つなのである──
次代のプロ作家を育てるオンラインサロン『「私」物語化計画』会員用Facebookグループ内の講義を、一部公開いたします。
ご興味をお持ちの方は、ぜひオンラインサロンへご参加ください。
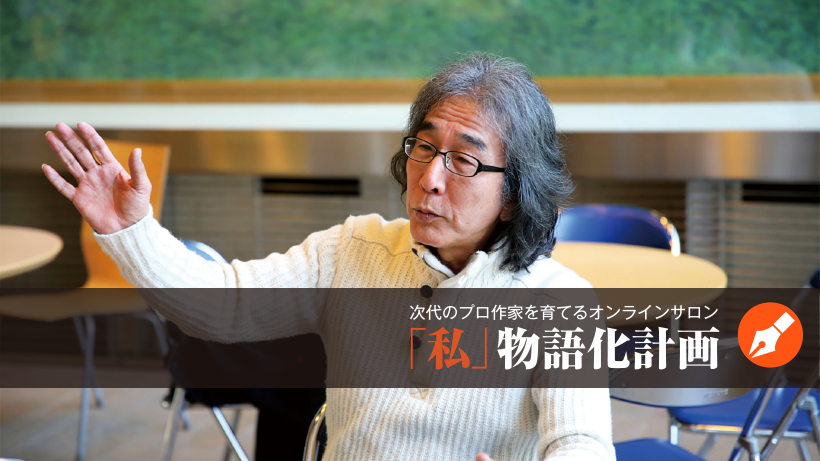
→ 毎週配信、山川健一の講義一覧
→ 参加者募集中→ 参加申し込みフォーム
2025年4月18日
特別公開:キャラクター・メーキングで失敗しないために 02 大江健三郎『日常生活の冒険』における認識者と行為者の原理を学ぶ 山川健一
【認識者と行為者】
大江健三郎氏に『日常生活の冒険』という長編小説がある。今週はこの作品からキャラクター・メーキングの技術を学んでいきたいと思う。
小説を書くときに、技術あるいは方法論は後付けである。まず書きたいコンテンツがあり、それを実現するための方法論を作家は身につけていくのである。
会員のNさんが書こうとしている小説を実現するために必要な方法論を、『日常生活の冒険』からピックアップしようと思うわけだ。この技術は、他の皆さんにも必ず役に立つはずである。
『日常生活の冒険』の大きな特徴は、明確に認識者と行為者が登場することだ。
あらすじをWikipediaから引用する。
若い作家である語り手「ぼく」のもとに、北アフリカから手紙が届。手紙は「ぼく」の友人の斎木犀吉の情人のイタリア人夫人M・Mからのもので、手紙によると犀吉が現地のホテルで自殺したという──(略)──それじゃ、さよなら、ともかく全力疾走、そしてジャンプだ、錘のような恐怖心からのがれて!」
大江健三郎『日常生活の冒険』
小説の主人公の「ぼく」は作品の語り手であり、「認識者」である。「行為者」は斎木犀吉である。
──(略)──
つまり大江氏が若い頃に書いた長編であり、本人は本作を「愛好してくださる読者はいまもあるようなのですが、技法、人物のとらえ方など、小説の基本レヴェルを満たしていない」として、1990年代にまとめられた選集『大江健三郎小説』には収録されていない。
ま、若い頃の作品であまり出来は良くない、ということなのだろう。しかし、大江健三郎の目の前には三島由紀夫や川端康成、谷崎潤一郎などの「日本文学」が立ちはだかっており、それを乗り越えて行くためにはこれぐらい荒唐無稽な物語が必要だったのだ。僕は後年の名作よりもこの情熱に溢れた『日常生活の冒険』の方が好きだ。
僕自身が小説を書き始めようとしていた若い頃────続きはオンラインサロンでご覧ください)
山川健一
『物語を作る魔法のルール
「私」を物語化して小説を書く方法』
(物語化計画ブックス)Kindle版
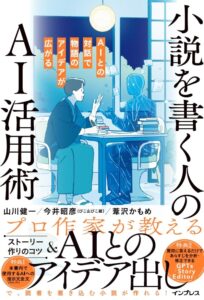 山川健一/今井昭彦/葦沢かもめ
山川健一/今井昭彦/葦沢かもめ
『AIとの対話で物語のアイデアが広がる
小説を書く人のAI活用術』(インプレス)
Amazon https://amzn.to/4dSXYLr
インプレス https://book.impress.co.jp/books/1124101059