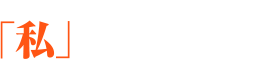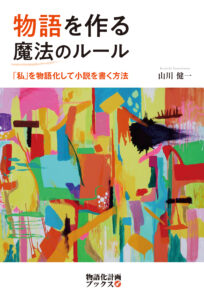キャラクター・メーキングで失敗しないために 01 「ざまあみろ」「絶対に許さない」はダメです 山川健一
──論理的に破綻がなく「正しい」作品であっても、登場人物たち、すなわちキャラに魅力がなければ、その作品に読者が感動する事はないだろう──
次代のプロ作家を育てるオンラインサロン『「私」物語化計画』会員用Facebookグループ内の講義を、一部公開いたします。
ご興味をお持ちの方は、ぜひオンラインサロンへご参加ください。
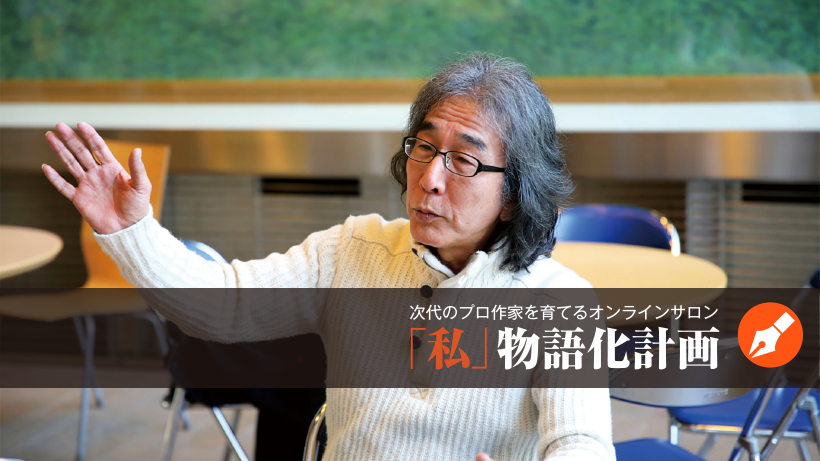
→ 毎週配信、山川健一の講義一覧
→ 参加者募集中→ 参加申し込みフォーム
2025年4月11日
特別公開:キャラクター・メーキングで失敗しないために 01 「ざまあみろ」「絶対に許さない」はダメです 山川健一
小説には間違いがある、ということをナラトロジーは指し示している。小説には、エモーショナルな側面と、論理的な側面がある。この論理を裏切ると、間違った作品になってしまう。そういうことを、物語化計画で、僕は長らく書いてきた。作品の冒頭には欠落がなければならない、というような物語の構造に関することだ。
しかし同時に、論理的に「正しい」作品が優れた作品であるわけでもない。論理的には、むちゃくちゃでも感動する作品はある。その辺が、小説の厄介なところだ。
小説のエモーショナル部分の解説は、論理的な部分の解説よりもはるかに難しい。しかし、最近会員の皆さんの作品を読みながら、そろそろ文学のエモーショナルな側面、生きた感情が呼吸しているのかどうか、というようなことを考えなければならないなと思うようになった。
この問題は、深くキャラクター・メーキングに関連している。論理的に破綻がなく「正しい」作品であっても、登場人物たち、すなわちキャラに魅力がなければ、その作品に読者が感動する事はないだろう。
ナラトロジー的には正しい作品でも、キャラクター・メーキング的には間違った作品というものがある。
それでは、厳しいようだがキャラクター・メーキングの失敗例を見ていこう。
【悲しみの不在】
あらゆる物語は、悲しみに満ちている。なぜか。すべての人間が、今、ここに生きていながらも、やがて死んでいくからだ。
そこに悲しみが生まれる。
悲しみのない物語は、物語とは言えないのである────続きはオンラインサロンでご覧ください)
山川健一
『物語を作る魔法のルール
「私」を物語化して小説を書く方法』
(物語化計画ブックス)Kindle版
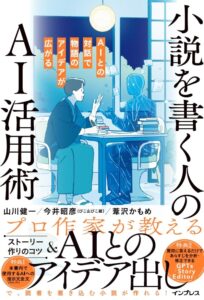 山川健一/今井昭彦/葦沢かもめ
山川健一/今井昭彦/葦沢かもめ
『AIとの対話で物語のアイデアが広がる
小説を書く人のAI活用術』(インプレス)
Amazon https://amzn.to/4dSXYLr
インプレス https://book.impress.co.jp/books/1124101059