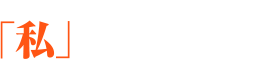『カラマーゾフの兄弟』から学ぶこと 07 幻覚がたんなるファンタジーではなく実在する何かであってほしい 山川健一
幻覚がたんなるファンタジーではなく、実在する何かであってほしい──というのはすべての作家の見果てぬ夢である
次代のプロ作家を育てるオンラインサロン『「私」物語化計画』会員用Facebookグループ内の講義を、一部公開いたします。
ご興味をお持ちの方は、ぜひオンラインサロンへご参加ください。

→ 毎週配信、山川健一の講義一覧
→ 参加者募集中→ 参加申し込みフォーム
2024年3月1日
特別公開:『カラマーゾフの兄弟』から学ぶこと 07 幻覚がたんなるファンタジーではなく実在する何かであってほしい 山川健一
【「悪魔。イヴァンの悪夢」について】
善人しか出てこない小説はつまらない。むしろそんな作品はあり得ない。悪人が登場するからこそストーリーが生まれるのだ。
その悪人が「悪魔」だということになれば、読者はいきなり作品に引き込まれるだろう。『カラマーゾフの兄弟』の凄さはそこにある。
スメルジャコフとの三度目(最後)の面談を終えて家に帰ったイヴァンは奇妙な紳士の来訪を受ける。部屋に入ったときにはまだいなかった人物だ。
第十一編九章「悪魔。イヴァンの悪夢」で描かれる話である。
黒っぽい髪の毛にも、くさび形に刈りこんだ顎ひげにも、まだそれほど白髪は目立っていなかった。
この男が、自分は悪魔だと名乗るのだ。
彼はそろそろ50歳に手の届く年頃だが、一昔前の高等遊民的地主の部類に属する感じである。かっては上流の社交界にも出入りし、さまざまな縁故も持ち、しかし最近になって農奴制も廃止され、しだいに落ちぶれた。やがて気のいい昔なじみの家を転々として歩く一種の上品な居候になりさがる。旧友たちのほうは、人づきあいのいい、これといって難のない彼の人柄を見込んで出入りを許しているのである。
イヴァンは憎々しげに黙りこくって、話しかけようともしない。客はじっと坐って待っている。それでも主人のほうから口を切ってくれさえすれば、どんなおべんちゃらでも即座にはじめられる用意はできているらしい。
この客が実は自分は「悪魔」なのだと名乗るわけだが、いかにもぱっとしない風体だ。服装も流行おくれだし、ワイシャツは薄汚れ、ネクタイもよれよれになっている。
なぜ悪魔はこんな風采の上がらない出立ちなのか?
それは、イヴァンの分身だからなのだと僕は思う。
最初から「悪魔」はイヴァンと「きみ・ぼく」というフランクな感じで話す。少なくともイヴァンとは旧知の間柄なのだろう。
イヴァンは現在23歳である。そのイヴァンは、そろそろ50に手の届くこの居候──悪魔を「ぼく自身の分身だ」と言う。
不自然だろうか?
しかし、もし────続きはオンラインサロンでご覧ください)
 山川健一『物語を作る魔法のルール 「私」を物語化して小説を書く方法』
山川健一『物語を作る魔法のルール 「私」を物語化して小説を書く方法』