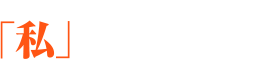特別公開:トーマス・マン『ベニスに死す』のメタファーの構造を移植する 山川健一
新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の危機のただ中にいる皆さんが、新しい小説をどう発想したらいいのかということを書く。
—
次代のプロ作家を育てるオンラインサロン『「私」物語化計画』会員用Facebookグループ内の講義を、一部公開いたします。
ご興味をお持ちの方は、ぜひオンラインサロンへご参加ください。

→ 毎週配信、山川健一の講義一覧
→ 参加者募集中→ 参加申し込みフォーム
「私」物語化計画 2020年4月24日
特別公開:トーマス・マン『ベニスに死す』のメタファーの構造を移植する 山川健一
今週の原稿は長くなりそうなのだが、なるべく簡潔にわかりやすく、短く書こうと思う。
新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の危機のただ中にいる皆さんが、新しい小説をどう発想したらいいのかということを書く。
感染症を前提にした代表的な、そして対照的な小説が2つある。1つは課題図書に指定したトーマス・マンの『ベニスに死す』であり、もう一つはアルベール・カミュの『ペスト』だ。
コロナの世界的な流行に伴い『ペスト』に対する関心が高まり、イタリア、フランス、イギリスなどでベストセラーになっているそうだ。日本でも小説の世界があまりにもコロナによる厄災と似ていることから、2020年4月には1969年から刊行されている文庫版の発行部数が累計で100万部を超えたと報じられた。『ベニスに死す』の方は、そういう話は聞かないが。
どちらの作品も、感染症による危機を前提に書かれた小説だが、『ベニスに死す』はコレラをメタファーとして扱い、『ペスト』は人間にとっての「不条理」であるペストを中心に据え、多くの登場人物たちがこれとどう戦うかという本格的な物語を構築している。『ペスト』を課題図書に指定しなかったのは、単純に長いからである。
それぞれがどういう方法論で書かれているかを見てみようと思うが、今週扱うのは『ベニスに死す』の方だ。
【『ベニスに死す』の構造分析】
トーマス・マン(Thomas Mann, 1875-1955)はドイツのリューベックの富裕な商家に生まれた。
僕は真冬のリューベックをドイツ製のクルマを運転して訪れたことがあり、東京に帰ってから『リューベックの二人』という短編小説を書いた。
バルト海に面した港町、リューベックは、西ドイツの美しい古都である。十四世紀の建物があちこちにのこり、石畳が敷きつめられ、昔の運河がそのまま流れている。
ハノーバーの空港でレンタ・カーを借り、アウトバーンを北上し、ハンブルクを過ぎる頃にはもう太陽は沈み、あたりは闇に包まれた。旅の疲れからか、中屋は助手席で眠っていた。ハンドルを握る妻の令子は、リューベックへの出口を見落とさないよう、標識に目をこらした。山川健一デジタル全集 Jacks『リューベックの二人』
ま、そういう街である。
マンは経済的に恵まれた人生を送った人で、代表作は何といっても教養小説の傑作『魔の山』で、1929年にノーベル文学賞を受賞した。『ベニスに死す』はルキノ・ヴィスコンティ監督による同名の映画が1971年に公開されたことで有名になった。
こんな書き出しである。
グスタアフ・アッシェンバッハ──または、かれの五十回目の誕生日以来、かれの名が公式に呼ばれていたとおりに言うと、フォン・アッシェンバッハは、一九××年──これはわれわれの大陸に対して、幾月ものあいだ、じつに脅威的な様子を見せた年だったが──その年の春のある午後、ミュンヘンのプリンツレゲンテン街にある自宅から、ひとりで、かなり遠くまで散歩に出かけた。
『ヴェニスに死す』トオマス・マン/実吉捷郎訳
真ん中を飛ばして、結末部分は以下の通りだ。
何分か過ぎてからようやく、人々は、いすの上で横むきにつっぷしてしまったこの男を救いにかけつけた。かれは自分の部屋へ運ばれた。そうしてまだその日のうちに、うやうやしく心を打たれたひとつの世界が、かれの訃報に接したのであった。
『ヴェニスに死す』トオマス・マン/実吉捷郎訳
今週、会員の何人かの方から「課題図書がむずかしくてよくわからない」「映画もダラダラしていて面白くない」などという感想がメールで届いたが、それは僕らが懇切丁寧なエンターテインメント小説やアメリカ映画に慣れてしまっているからなのだ。
この程度で音を上げてはいけない。
主人公は著名な作家グスタフ・フォン・アッシェンバッハである。映画では小説家ではなく作曲家という設定になっている。
アッシェンバッハは執筆に疲れて英国式庭園を散策した帰り、異国風の男の姿を見て旅への憧憬をかきたてられる。そこでアドリア海沿岸の保養地に出かけたが、そこに嫌気がさしてヴェネツィア(ベニス)に足を向ける。
ホテルには長期滞在しているポーランド人貴族の一家がおり、その10代はじめと思われる息子タージオの美しさに魅せられてしまう。
海辺で遊ぶ少年の姿を見るだけでは満足できなくなり、後をつけたり家族の部屋をのぞきこんだりするようになる。
既に初老の威厳ある作家である彼は、美少年への恋にのめりこんでいく。しかし、ヴェネツィアにはコレラが迫っていた──という展開だ。
あちこちを消毒する様子を不審に思ったこの作家は、街の男やホテルの支配人を問いただすが、観光地であるヴェネツィアの人々はコレラについては口を閉ざす。
誰も真実を語らない中、ようやく疫病が流行していることを聞き出した。それでも彼はヴェネツィアを去らない。美少年と別れることが出来ないからだ。
滞在客たちが逃げ出しヴェネツィアは閑散とするが、アッシェンバッハは白髪染めを施して若作りをし白粉と口紅までつけて、死臭漂う街を美少年・タージオの姿を追い求め歩き続ける。
街を脱出するための交通機関が遮断される日、少年一家は急ぎ足でヴェネツィアを旅立っていく。
アッシェンバッハは少年の幻を思い描きながら歩き続け、ついに街中で倒れ込み、ひとり力なく笑い声を上げる。
翌日、疲れきった体を海辺のデッキチェアに横たえ、波間の光がきらめく中、彼方を指差す幻想としてのタージオの姿を見つめながら彼は死んでゆく。アッシェンバッハはコレラに感染していたのである。
ストーリーだけ語れば、以上の通りである。
秀逸なのは、コレラの扱い方だ。
街の全体に何か危険が迫っていることがわかるのだが、その正体がなかなか明かされない。それがコレラの感染拡大だと分かる頃には、主人公の作家は街を去ることができなくなっているわけだ。
アッシェンバッハにとってコレラという疫病の脅威が少年愛という魂の危機のメタファーになっている。
この方法論なら、カミュの『ペスト』と異なり、感染のことを踏み込んで描く必要がない。あくまでも小説のバックボーンに疫病的な危機が進行している──という構造にすれば良いのである。
この構造は、皆さんが書こうとする作品に移植しやすいはずである。
【作品例/怪物と心優しい妖精】
COVID-19をメタファーにしてプロットを立ててみなさい──と会員の皆さんに言うのは簡単だが、無責任でもあるだろうから、僕自身がこの方法論で具体的なプロットを立ててみる──続きはオンラインサロンでご覧ください)