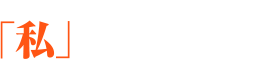特別公開:基礎的な文法の話──文法とはあなたが書きたい言語の召使いなのである 山川健一
大切なのは、まず「何を書きたいか」ということが先にあり、言葉はそれを実現するために創造されたのだということだ。言語が発達したから物語が生まれたのではなく、物語を紡ぐために言語が作られていったのである。
—
次代のプロ作家を育てるオンラインサロン『「私」物語化計画』会員用Facebookグループ内の講義を、一部公開いたします。
ご興味をお持ちの方は、ぜひオンラインサロンへご参加ください。

→ 毎週配信、山川健一の講義一覧
→ 参加者募集中→ 参加申し込みフォーム
「私」物語化計画 2020年1月10日
特別公開:基礎的な文法の話──文法とはあなたが書きたい言語の召使いなのである 山川健一
都内のマクドナルドの大きなテーブルでビッグマックのセットを食べていたら、隣に男子高校生の4人グループがやってきた。高校生らしい部活やゲームの話をしていたかと思うと、1人がこう言った。
「シンギュラリティって知ってるか?」
もう1人が即座に答える。
「人工知能が人間の知性を追い抜くってことだろ」
なかなか知性的な高校生たちだ、と思い僕は耳を澄ませた。
シンギュラリティ(Singularity)は技術的特異点と翻訳されており、人工知能自身が自己フィードバックで自らを改良し続け、高度な技術や知能を得るようになり、人類に代わって文明の進歩の主役になる時点の事だ。シンギュラリティ・ポイントと言ったりする。
高校生たちの話はあちこちに飛んで、聞いていて飽きない。「渋谷のスクランブル交差点の大勢の歩行者たちを、AIは人間と認識できないんだってよ。だから自動運転には限界があると俺は思う」という意見、「今だってゲームのキャラはリアルな女子よりもかわいいんだからさ、あれが3DになりAIを搭載したら誰も恋愛なんかしなくなるよね」という意見もあった。
アメリカがイランの司令官をミサイルで殺したのもAI を積んだドローンだったんだよな。
ある日ネットワーク化されたAIが人類の歴史をリサーチして、こんな連中は地球にとって害しかもたらさないという結論に達して核のボタンを押したらおしまいだよな──と話は続く。
やがて1人がこう言った。
「そんなことよりさ、俺たちがやれる仕事なんてなくなるんじゃね?」
それからしばらく、4人の男子は黙り込んでしまったのだった。
時代は本当に変わったのだな、と僕は考えた。僕が高校生の頃はロックバンドで成功したいとか、ランボーやドストエフスキーはすごいなとか、そんなことしか考えていなかった。
しかし今や、シンギュラリティ・ポイントが迫っているのだ。それは、冗談ではなく、今年なのかもしれない。
アメリカとイランの間の戦闘がどうなっていくのか、予断を許さない状況だ。イランがイスラエルに核ミサイルを打ち込めば、あっさり第三次世界大戦だ。
そして日本の若者たちは、いや若い世代ではなくすべての世代が、貧困化している。今の高校生はそんな中で未来を切り拓いていかなければならないのだ。
文学も変わらなければならない。
安易な希望を描いても、誰も信用しないだろう。ネガティブな未来だけを描く小説なんて、誰も読みたくはないだろう。そういえばAIが書いた小説が文学新人賞の最終候補に残ったというニュースもあった。
さて、2020年、僕らはどんな小説を紡げばいいのだろうか?
──というのが、僕の年頭の挨拶です。今年もよろしくお願いします。
昨年末は文法の話が続いたが、今年はまずガルシア・マルケスの『百年の孤独』の有名な冒頭部分について考えてみよう。
《長い歳月が過ぎて銃殺隊の前に立つはめになった時、恐らくアウレリャーノ・ブエンディア大佐は、父親に連れられて初めて氷という物を見に行った、遠い日の午後の事を思い出したに違いない。》(ガルシア・マルケス『百年の孤独』新潮社)
なに、これ?
それがマルケスを初めて読む人の感想だろう。僕もそうだった。
日頃読み慣れた日本文学に比べてあまりにも一文が長い。しかも意味がよくわらない。
長い歳月が過ぎて──いつから?
恐らくアウレリャーノ・ブエンディア大佐は──誰がそう言ってるのか? つまり誰の視点?
初めて氷という物を見に行った──どういう意味?
いろいろ不可思議だが、しかしこの冒頭の一文でもっとも奇怪なのは文末の「違いない」だろう。
冒頭部分の「主部」は言うまでもなく「アウレリャーノ・ブエンディア大佐は」であり、述部は「思い出したに違いない」である。
普通に書けば「アウレリャーノ・ブエンディア大佐」という主語を「思い出した」という述語が受ければいいのだ。だがマルケスはそう書かなかった。
なぜ?
文法的に言えば三人称であり、小説的に言えば神の視点である。だがこの冒頭部分は、普通の三人称小説であれば「思い出した」と断定するところを「に違いない 」と判断を留保している。
つまり三人称の語り手なのだが神ほどには全能ではなく、全てを知ることはできない。だからこそ語り手が小説世界の中に「いる」感じがする。そこに読者は奇異な感じを受けるのではないだろうか。
すなわち、神の視点と言うよりは「百年」という時間がこの物語を語っているのだ。そうとしか読めない。
ジャングルにマコンドという架空の街が生まれ、幾世代かの狂騒が大地に飲み込まれ、吐き出される。ビルが立ち、鉄道が走り、壮大な規模のプランテーションが生まれ、長い雨が降り続いた後、最後に一陣の風が吹いて砂埃を巻き上げると、それは最初から何もなかったように消え去ってしまう。
まるで魔法のようではないか!
そう、ガルシア・マルケスの『百年の孤独』は、マジックリアリズムであるとされている。
マジックリアリズムというのは…..,(特別公開はここまで、続きはオンラインサロンでご覧ください)